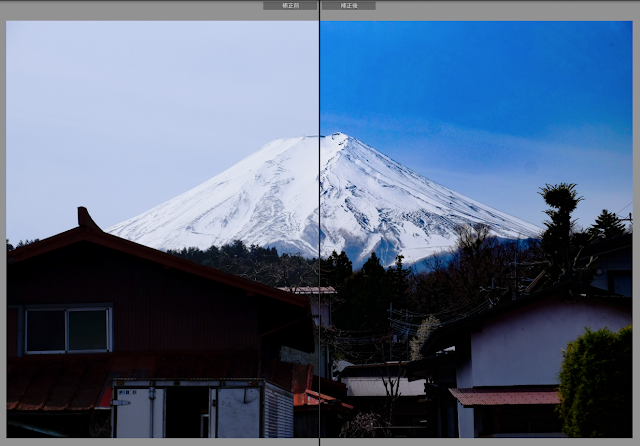仕事がない晴れた日は趣味に走るべしpart2
ということで……毎週そんなことやってる気がするんだが
……仕事下さい。
はともかく、
足立区の古道はほぼ手つかずだったので今年中にあれこれ訪れたいとずっと思ってたとき
西新井大師で風鈴祭りが開催されてると聞き、
よしそれにしようと北千住へ。
今日のお供は、いつものOM-D E-M1とパナソニックのCM1。
iPhoneはログ撮りや地図で忙しいので、
スナップは全部CM1で撮ってみた。まあこっちの方が基本性能が高いので便利。
辿るのは大師道か芳賀善次郎氏が鎌倉古道と推定した道か、まあ大師道を「推定鎌倉街道支線」とする考えもあり、千住から奥州へ向かう鎌倉古道(の支道)には候補が2本あるということだが、
今回は、最終目的地が西新井大師ということもあって「大師道」を辿ることに。
まずはログ。
FieldAccess 2で明治の迅速図に薄く現代の国土地理院地図を重ね、その上にログをのっけ、
Skitchで注釈を付けてみた。全部iPad上での作業。
これをやると、鉄道や今の街道、川筋が薄く透けるのでその位置関係がわかりやすい。
今回は特に大正〜昭和初期に作られた「荒川放水路」(あれ、人工の川です)の影響が如何に大きかったかが見てとれる。
あたまでわかってても、荒川(放水路)の北と南で別の地域って感じがしちゃうもの。
ともあれこんな感じ。
北千住駅から旧日光街道を南下してまずは氷川神社。
千住あたりはとにかく「氷川神社」だらけ。
荒川流域は氷川が強いのだ。
・仲町氷川神社
牛田(北千住の南東あたり)にあった氷川神社を1616年にここに遷座したとか。
江戸時代には白幡八幡神社もここに合祀されていたもよう。
(地図の右下にある氷川神社)。
 |
| 仲町氷川神社。DMC-CM1 |
・白幡八幡神社
源義家が白旗を戦勝祈願したのがはじまりという。それがこの場所であったかはよくわからないが、江戸時代は仲町氷川神社に合祀されていたらしい。
・千住神社
北千住の神社といえばここ。旧日光街道筋から離れているが、鎌倉古道筋なのでこの場所でよいのだ。
 |
| 千住神社。E-M1 |
926年創建の稲荷と、1279年の氷川(ここにも氷川!)が並んでて、「二つ森」と呼ばれていたのが元。大正になって2つの神社をいっしょにして千住神社と改称。
一の鳥居のすぐ脇に「史跡 八幡太郎源義家陣営の地」とある。
源義家が奥州へ向かう際、ここに陣を張ったという話。
浅草橋の銀杏八幡、さらに鳥越神社、浅草を超えて今戸神社と義家伝承が南北に並んでいるのがミソ。
今日はとにかく暑くて蒸しててこんな日にひとりで古道散歩なんてアホだなと思ってはいたが、さすがに千住神社ほどの神社になると風が通ってて涼しい。
喫煙所でくつろいでると、光化学スモッグ注意報の放送が流れる。なんてこった。
ともあれ、ここで帰るのもばかばかしいので西新井大師へ向かう。
墨堤通りをまっすぐに進む。江戸時代に隅田川の堤防として作られたのが墨堤。
江戸時代に作られた堤だからここを鎌倉古道が通っていたわけがないという人もいるが、堤が作られる前は川が作った微高地だったんじゃないかと思う。千住神社の立地条件をみるにつけ。であれば、ほぼ同等の道筋であっても不思議はあるまい。
今でも墨堤通りだけ両脇より少し高いのが面白い。
・元宿神社
しばらく進み、現荒川に近づくとそこは「元宿」。千住宿の元々の場所で、平安時代から中世はここが「千住」の中心であり、宿だった。
元宿堰稲荷を参拝したあと、元宿神社へ。
ここは氷川ではなく、八幡。
 |
| ここが八幡だったころの名残。元宿神社。E-M1 |
・西新井橋
荒川放水路建設のために、かつて元宿を開拓した鈴木氏が先祖伝来の土地を奪われたと切々と語る「感旧碑」が元宿神社にある。
上の地図を見ると、荒川放水路が道も集落も流してしまったのがわかる。
古道を辿るときも大変。
・神社銀座←勝手に名付けた
川を渡ると、西へ向かう。本木のあたりは神社の宝庫。
とりあえずいけるところは全部回るつもりで。
本木氷川神社、北野神社、胡録神社、熊野神社。
狭い地域に4つの神社が集まってるんだけど、それぞれ別の場所なので
地図を見ながら迷いつつ訪問。
あ、熊野神社に行きそびれた! 今気づきました。がーん。
今度リベンジしなければ。氷川から元の道に戻らずにそのまま北上すればよかったのか。ちょっとショック。
・中曽根城址
このあたり、古道の道筋がけっこう生きてて素晴らしい。
 |
| CM1 |
その大師道を北へ向かう途中、東にそれ、中曽根神社へ立ち寄る。
ここ、戦国時代の中曽根城址(千葉氏の居館)なのだ。淵江城ともいう。
 |
| 中曽根神社が中曽根城址。E-M1 |
大師道と鎌倉古道といわれてる道のちょうど中間にある。
・興野氷川神社
そして大師道へ戻るとまた氷川神社。興野神社。
・西新井大師
ここからはもうまっすぐ、ときどきコンビニで涼みつつ、西新井大師へ。
風鈴祭りは最終日で到着したときは16時過ぎでもう大物は売れちゃってたみたいでちょっと寂しかったけど、十分涼めました。
 |
| DMC-CM1 |
西新井大師って、新井薬師(こっちは中野区)と紛らわしい名前でいかんですな。
なぜ西新井なのか、どれだけ古地図を見たり歴史を辿っても、新井村や東新井村はないぞ、と思ったら、このお寺の「西にある涸れ井戸から水が出た」←「西の新しい井」という伝承があるらしい。
→
西新井大師のご案内 | 西新井大師
わはははそれは意表をつかれたわ。
西新井大師、弘法大師が創建というから9世紀創建か。
まあ弘法大師が創建したとか弘法大師が見つけた井戸は全国に無数にあるのでアレなんだが、ここは古そう。
・大師前駅
さて目的も達成したので帰る。
西新井駅まで歩こうかと思ったら、大師前駅が面白い。
無人なのだ。改札がないのだ。中に入り放題なのだ。
 |
| 大師前駅。改札はあれどあけっぱなし。CM1 |
入ってみると、単線なのに無人駅とは思えないほど広い。
初詣客をさばくためだろう。
ついひと駅だけ電車に乗る。
乗るのは無料だけど、西新井駅で改札を通るときお金を払うわけで、よくできたシステムである。ひと駅だけだからできたんだろな。
ちなみにこの大師線、もともと西板線といって、東武東上線の上板橋駅まで伸びる予定だったんだそうな。でも頓挫し、ひと駅分だけ残ったのである。面白い。
西新井から東武線で北千住へ行き、そこで千代田線に乗り換えて帰宅。
西新井駅で掲示板を見ると、行き先が中央林間(東急田園都市線!)、中目黒(東京メトロ日比谷線!)、浅草(東武伊勢崎線)とすごいバリエーションでややこしい。
東武線って浅草起点ってイメージがあったのだけど、それも過去のものなのであるなあ。
 |
| 西新井駅ホームにて。CM1。 |
いやあ、暑くて死ぬかと思ったけど無事帰還。
大師道は鎌倉古道かといわれると、なんとなく用水沿いに作られた江戸時代の、西新井大師詣でが流行した頃の道のような気がする。
今度はもう1本のルートをたどってみることにする。